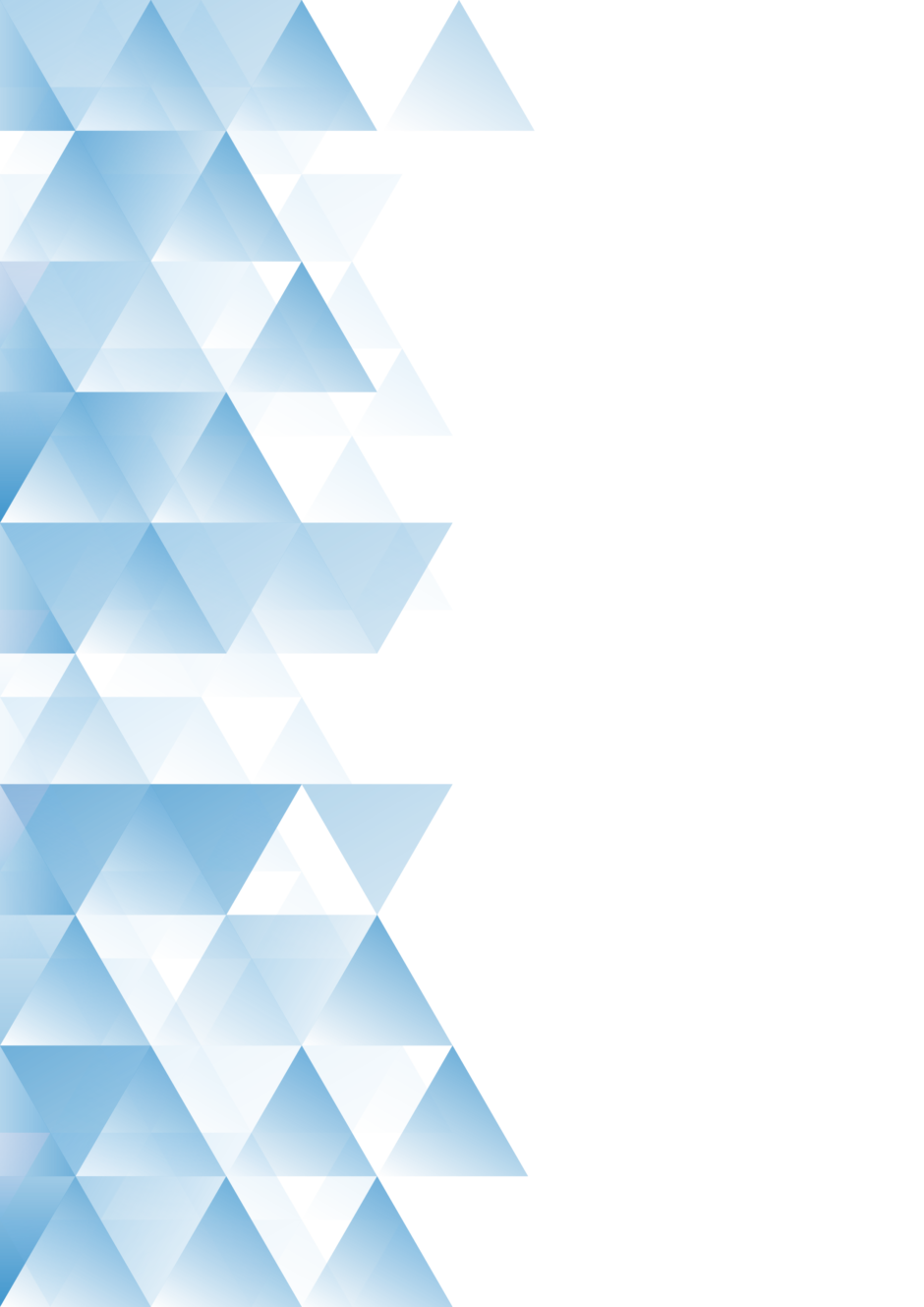ヘパリン類似物質ローションが「乳液性」と「水性」に分裂!?
〜薬剤師が泣いたり笑ったりする2025年夏の処方箋事情〜
序章:「えっ、同じじゃなかったの!?」
2025年8月14日――この日は薬剤師たちにとって、地味ながらも忘れがたい一日になりました。
理由は単純明快。
それまで「ヘパリン類似物質外用液0.3%」として一括りにされていた保湿薬が、「乳液性」と「水性」に分かれて収載されたのです。
患者さん視点では「そんなのどっちでもいいじゃん」「同じ薬でしょ?」と思うかもしれません。
しかし薬剤師の視点では、
- 処方箋チェックの手間が増える
- 疑義照会の件数が増える
- 在庫管理が複雑化する
- 服薬指導が細分化される
と、けっこうインパクトのある改訂なのです。
イメージで言うなら、長年「ファンタオレンジ」として売られていた飲み物が、急に「炭酸強めファンタオレンジ」と「炭酸弱めファンタオレンジ」に分けられたようなもの。
飲む人にとっては「まあ、どっちでもオレンジ味だよね」と思うでしょう。
でもコンビニの店員からしたら「どっち置く?棚どうする?間違えたらクレーム…」と頭を抱える事態。
薬剤師もまさにそんな状況に陥っています。
第1章 そもそもヘパリン類似物質って何?
1-1. 保湿薬界のオールラウンダー
ヘパリン類似物質は、血液をサラサラにする薬「ヘパリン」と似た構造を持ちながら、外用薬としては 保湿・血行促進・軽度の抗炎症作用 を発揮する成分です。
つまり、肌が乾燥してバリア機能が壊れているときに「修復のお手伝い」をしてくれる便利な存在。
臨床現場では以下のような場面で大活躍しています:
- 乾燥性皮膚炎
- アトピー性皮膚炎
- 角化症
- 褥瘡や外傷後の瘢痕治療
- 放射線皮膚炎のケア
まさに「皮膚トラブルとりあえずの1本」みたいな立ち位置です。
1-2. 日本人とヘパリン類似物質の深い仲
冬場になると「乾燥するからヒルドイド出しておいて」と言われるほど、生活に密着しています。
小児科では乳児湿疹に、小児の乾燥予防に。
高齢者では皮膚の乾燥や掻痒症の改善に。
働き盛りの世代ではアトピー治療や美容目的での使用も(美容皮膚科界隈では「高級保湿薬」として一時バズったほど)。
つまり、老若男女に幅広く使われる「国民的スキンケア薬」と言えるでしょう。
第2章 乳液性 vs 水性、その違いはどこに?
ここからが今回の大問題。
なぜ「乳液性」と「水性」に分ける必要があったのでしょうか?
2-1. 製剤学的な違い
乳液性(エマルジョン型)
- 白濁した見た目、乳液っぽい。
- O/W型(油が水に分散しているタイプ)のエマルジョン。
- 油膜を形成して水分の蒸発を防ぐ。
- しっとりするが、べたつきやすい。
水性(ローション型)
- 透明でサラサラ。
- 水溶性基剤を主体にしたローション。
- べたつきが少なく、使用感が軽い。
- ただし保湿力は乳液性に劣る。
同じ「ヘパリン類似物質0.3%」なのに、基剤が違うだけで患者の印象はまるで変わります。
2-2. ラーメン vs うどんで例えるなら
- 乳液性は「こってり豚骨ラーメン」。寒い日に食べると最高だが、夏場に食べると汗だく。
- 水性は「あっさり冷やしうどん」。暑い日でもスッと入るけど、冬にはちょっと物足りない。
医薬品の世界では「基剤の違い」は「服薬コンプライアンス」に直結します。つまり、いくら成分が同じでも「べたつくから塗りたくない」で投薬中断されると治療効果が落ちる。
そのため「乳液性か水性か」を選ぶことは、実は治療成績に大きな差を生むのです。
第3章 薬剤師の悲喜こもごも
さあ、ここからは実際の薬剤師業務で起きる悲喜劇を見ていきましょう。
3-1. 処方箋監査編
従来:
「ヘパリンローション0.3%、はいOK。調剤進めよう」
今後:
「ヘパリンローション0.3%…おや?乳液性か水性か書いてないぞ。えっと、先生に電話…」
疑義照会が頻発する未来が待っています。
医師も「え、そんなに違うの?」と最初は驚くはず。
3-2. 調剤室編
在庫管理が大変になります。
薬局の棚には「乳液性ローション」と「水性ローション」を両方ストック。
しかもメーカーによってはパッケージが似ているので、誤調剤のリスクが上がります。
現場薬剤師の声が聞こえてきそうです:
「また似たパッケージ!こっちは命がかかってるんだぞ!」
3-3. 服薬指導編
患者さんに説明するときも一苦労。
患者「先生、前と違う薬が出たんだけど」
薬剤師「いえ、成分は同じなんです。ただ、前は“こってりタイプ”、今回は“あっさりタイプ”なんです」
患者「ラーメンの話ですか?」
…こんな会話が日常的に発生するかもしれません。
第4章 季節ごとの攻防
皮膚は季節によって状態が大きく変わります。
「乳液性」と「水性」をどう使い分けるか、薬剤師は患者さんの生活習慣や気候に合わせて提案する必要があります。
4-1. 冬 ― 乾燥との戦い
冬は空気が乾燥し、暖房の風でさらに肌の水分が奪われます。
「かゆい!」「粉を吹く!」という患者が激増する時期。
ここでは乳液性ローションが圧倒的に優勢です。
油膜を作り、水分を逃がさないからです。
- 高齢者:皮脂分泌が低下しているので乳液性必須。
- 小児:アトピー性皮膚炎の悪化防止に乳液性が有効。
- 女性:化粧下地としてはやや重いので、顔には使い分けが必要。
薬剤師の一言:「この時期はこってりタイプ(乳液性)でしっかりガードしましょう!」
4-2. 夏 ― 汗と皮脂のWパンチ
高温多湿の日本の夏。
患者さんの声は「べたつくから塗りたくない!」に尽きます。
ここで水性ローションの出番です。
- サラッとして塗りやすい
- 冷蔵庫で冷やして使うと爽快感UP
- 部活動やスポーツをする学生にもおすすめ
薬剤師の一言:「夏はあっさりタイプ(水性)で快適に保湿しましょう!」
4-3. 梅雨と秋 ― 中途半端な時期のジレンマ
梅雨:湿気でベタつくけど、冷房で乾燥もする。
秋:夏のダメージが残りつつ、空気が乾燥し始める。
この時期は「乳液性と水性を部位ごとに使い分け」がベスト。
- 顔や首:水性で軽く
- ひじ・すね・かかと:乳液性でしっかり
薬剤師の一言:「部位ごとにラーメンとうどんを食べ分けるイメージです」
第5章 現場でのトラブル予想
5-1. 医師との会話
医師「ヘパリンローション出しておいて」
薬剤師「先生、乳液性ですか?水性ですか?」
医師「え?違うの?」
薬剤師「違うんです!使い心地が全然違います!」
疑義照会が全国で多発する未来は容易に想像できます。
5-2. 薬局の棚事情
これまでは「ヘパリンローション」と一括りで在庫管理できました。
今後は「乳液性」「水性」「クリーム」「ソフト軟膏」と4種類をそろえる必要が出てきます。
薬剤師A:「もう棚がパンパン…」
薬剤師B:「冷蔵庫もいっぱい…」
薬局長:「在庫管理表の列がまた増えるじゃないか!」
5-3. 患者の混乱
患者「前と違う薬が出たんだけど」
薬剤師「同じ成分ですよ。今回はあっさりタイプ(水性)です」
患者「いやいや、味の話してませんよ」
…こうしたやり取りは必至です。
第6章 薬剤師が生き延びるためのマニュアル
薬剤師はこの混乱をどう乗り切るべきでしょうか?
6-1. 処方箋監査での鉄則
- 「乳液性」か「水性」かを必ず確認。
- 書いていなければ疑義照会。
- 一般名処方マスタ改訂後は、監査システムで警告が出るようになる可能性も高い。
6-2. 調剤時の工夫
- 薬袋に大きく「乳液タイプ」「水タイプ」と明記。
- 在庫棚にも「赤ラベル=乳液性」「青ラベル=水性」などの工夫。
- ダブルチェックを徹底して誤調剤を防ぐ。
6-3. 服薬指導の必殺フレーズ
- 「冬はこってりラーメン、夏はあっさりうどんです」
- 「顔にはさっぱり(水性)、ひじやかかとにはしっとり(乳液性)」
- 「同じ成分なので安心してください」
ユーモアを交えることで、患者の理解が深まり、信頼関係も築けます。
第7章 ちょっと専門的なお話(補足)
ここからは大学院生や医療従事者向けの少し高度な内容です。
7-1. 製剤安定性
- 乳液性:界面活性剤を用いるため、分離リスクがある。保存条件に注意。
- 水性:比較的安定性が高い。冷所保存不要。
7-2. 臨床試験データ
- 乾皮症改善率:冬季は乳液性が有意に高い。
- 使用感評価:夏季は水性が有意に高い。
- 患者満足度:季節ごとに差が出る。
7-3. 海外の状況
欧州ではすでに「O/Wエマルジョン型」「水溶性ローション型」として区別されている。
今回の日本の改訂は、国際的な製剤区分に追随した形。
第8章 未来予想図
8-1. 医師への教育
処方意図を明確に書いてもらう必要があります。
「冬だから乳液性」「夏だから水性」といった選択を意識してもらう。
8-2. 薬剤師の役割強化
患者に「使い分け」を説明できるのは薬剤師の強み。
薬剤師が「お肌のコンサルタント」として地位を高めるチャンスです。
8-3. 患者教育の未来
パンフレットやイラストで「乳液性と水性の違い」をわかりやすく説明する必要があるでしょう。
AIアプリで「今の季節なら乳液性をおすすめします」と表示する時代も来るかもしれません。
まとめ:「面倒?それともチャンス?」
確かに今回の改訂は、薬剤師にとっては手間が増える出来事です。
でも裏を返せば、患者さんに合わせた“オーダーメイド指導”ができるようになる進化とも言えます。
- 冬は乳液性(こってりラーメン)
- 夏は水性(あっさりうどん)
このシンプルな図式を覚えておけば、患者さんも納得してくれるでしょう。
そして患者さんから「先生より説明わかりやすい!」と言われたら、それは薬剤師冥利に尽きる瞬間です。